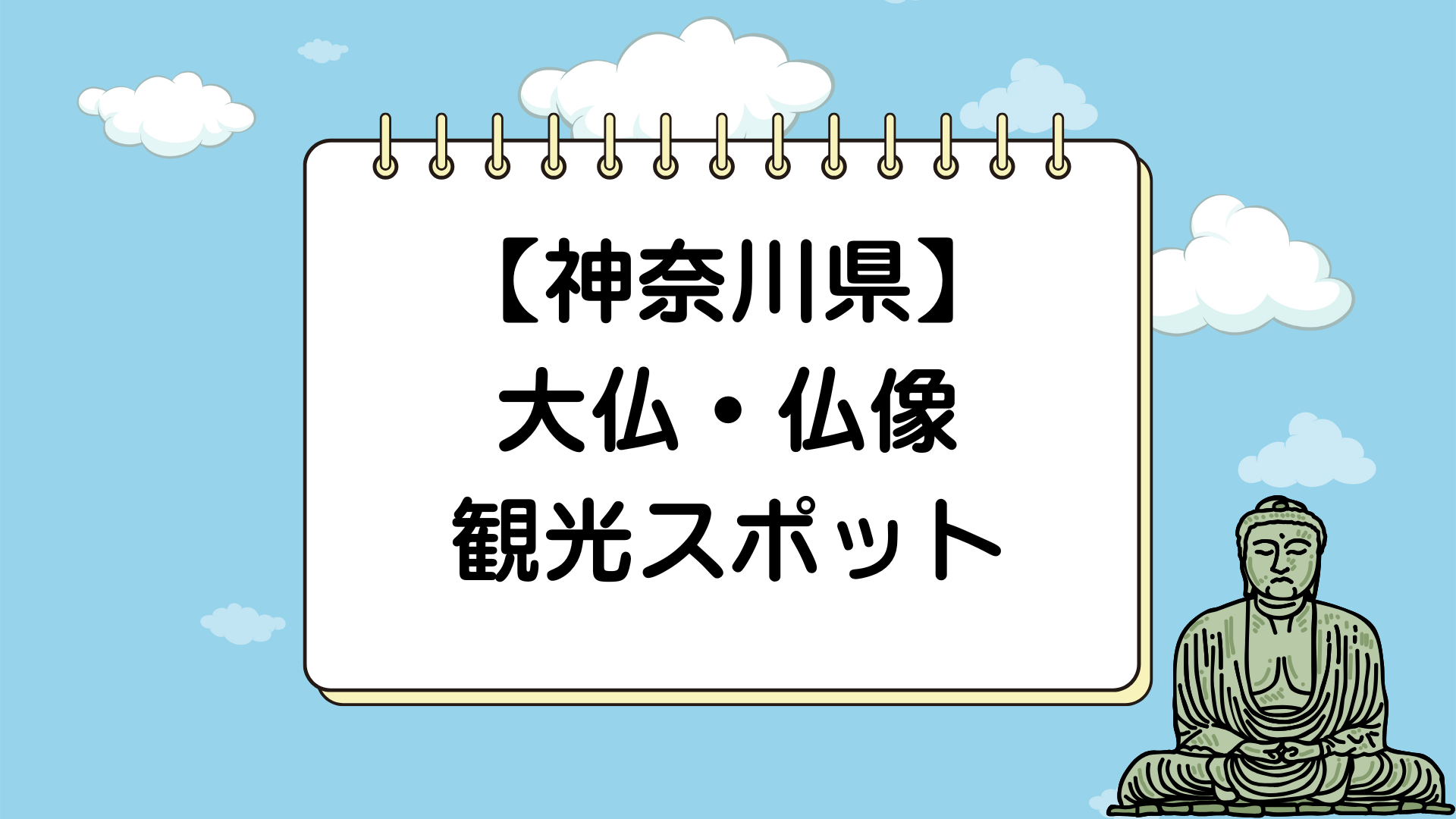神奈川県のなかで、大仏や仏像を見ることができる観光スポットを紹介していきたいと思います。
全国的に知名度の高い、“鎌倉大仏”をはじめ、趣深い名所ばかり。ぜひ旅の参考にしてみてください。
高徳院(鎌倉大仏)

- 国宝の鎌倉大仏が見られる
- 最寄り駅は長谷駅
“鎌倉大仏”や“長谷の大仏”として知られるこちらの阿弥陀如来坐像(あみだにょらいざぞう)。
1252年ごろからから建立が開始したとされています。もともとは大仏殿のなかに安置されていましたが、強風や地震などの点背愛により、露坐( 屋根のない所にすわること)の大仏となりました。
「鎌倉の大仏」というイメージが強いので間違いやすいのですが、最寄り駅は鎌倉駅ではなく長谷駅です。

長谷寺
- 観音ミュージアムが併設されている
- 最寄り駅は長谷駅(鎌倉大仏とあわせて観光しやすい)
こちらも最寄り駅は長谷駅。正式名称を「海光山慈照院長谷寺」といい、日本三大長谷観音に数えられるお寺です。
本尊は十一面観世音菩薩像。高さ9.18mで、木彫仏としては日本最大級とのこと。その名の通り、頭の上に十一の顔を並べているのが特徴です。本堂(観音堂)に安置されています。
本堂に向かって右手には阿弥陀堂があり、阿弥陀如来坐像を安置。鎌倉幕府初代将軍である源頼朝が42歳のときの厄除けのために作られたとされています。
また本堂に向かって左手にあるのは観音ミュージアム。観音菩薩を主題とした博物館です。「観音三十三応現身像」がずらりと並ぶ展示は圧巻です。
ぜひ鎌倉大仏とあわせて観光したい場所と言えますね。
大船観音寺
- 大仏の胸像が見られる
- 胎内にも入れる
- 最寄り駅は大船駅
歴史は比較的浅いものの、あまり見ない胸像の仏像が見られるお寺です。胎内に千体仏が収められていて、そこへ入ることもできます。
昭和2年2月から企画され、昭和4年4月から着工。もともとは約9mほどの坐像になる予定でしたが、地形にあわないなどの理由から胸像となるに至ったそうです。
その後、世界的な情勢の不安定さもあり、しばらく工事は中断されていましたが、昭和32年から工事が再開。そしてついに昭和35年4月に完成しました。
仏像はもちろんですが、大船の街を一望できる絶景ポイントや、良縁成就・夫婦円満のご利益があるとされる縁結びの木など、見どころが盛り沢山です。
極楽寺
- 日本遺産のお寺
- 4月7~9日のみ本堂に入堂できる
- 最寄り駅は極楽寺駅
1259年、北条氏が創建した日本遺産のお寺です。火災による焼失と復興を何度も繰り返してきた歴史があります。
本堂には、中央に不動明王坐像、向かって右側に薬師如来坐像、左側に文殊菩薩坐像が安置されていますが、本堂に入れるのは4月7~8日の2日間のみ。
短い期間ですが、咲きほこる桜を楽しめる可能性も。
併設されている宝物館にも重要文化財の釈迦如来坐像などが安置されています。ただ、こちらも開館時期が限られていて、4月25日~5月25日と10月25日~11月25日の、しかも火・木・土・日曜のみ開館(雨天休館)です。
やや訪れるハードルは高いかもしれませんが、だからこそ一度は訪れてみたい場所です。